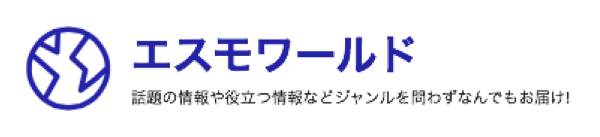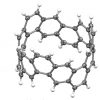大晦日(おおみそか)の名前の由来とは?おおつごもりとも読む?晦の意味についても
公開日:
:
豆知識
今年もまもなく終わり大晦日(おおみそか)を迎えますが、大晦日の名前の由来とは何なのでしょうか?
そもそも大晦日の「晦」とは一体どういう意味なのでしょう?
今回は気になるこれらの情報についてまとめてみました。
大晦日とは?
大晦日とは、1年の最後の日を指します。
旧暦では12月29日で、現在の新暦では12月31日となっています。
大晦日の読み方は”おおみそか”ですが、”おおつごもり”とも読むとのこと。
大晦日の名前の由来とは?
では大晦日の名前の由来とは何なのでしょう?
大晦日の晦日(みそか)というのは毎月の最終日という意味でした。
というのも”おおみそか”の”みそ”というのはもともと”三十”の読みであり、”みそか”は30日の意味でした。
実際月の終わりは29日だったり、31日だったりもしますが、”みそか”はその日付に関わらず月の最終日を示す言葉となりました。
そして12月31日は月の最後であり、1年という大きな期間の終わりでもあるので、大きな晦日ということで大晦日になったということです。
晦とは?
ところで、大晦日の「晦」という漢字はどこから来ているのでしょう?
これはもともと満月や新月などの月相を表す言葉でした。
月相は弦・望・晦・朔に分かれ、「朔」が月が現れることを意味するのに対し、「晦」は月が隠れることを意味していました。
晦日が毎月の終わりという意味になった理由は満月の中旬以降、月が徐々に見えなくなっていくことにありました。
また、大晦日は別名”おおつごもり”とも読みます。
これは月隠り(つきごもり)が転じてこう読まれるようになりました。
これらのことから大晦日の漢字には月が隠れるという意味の「晦」が入っているというわけなんですね。
大晦日の名前の由来を調べてみてなんだかとても納得しました。
この由来、豆知識としてぜひとも活用してみてください^_^
関連記事
-

-
6月6日はロールケーキの日!他にも同じ日がある?その由来とは?
6月6日はロールケーキの日だそうですが、その由来とはなんなのでしょう? 他にも同じロールケ
-

-
日本の光化学スモッグはどれくらい危険?中国との比較は?
日差しが強い時期になってくると光化学スモッグというものをよく見かけるようになりますが、日本の光化
-

-
3月27日はさくらの日!なんとも微妙なその由来とは?
みなさんは3月27日が「さくらの日」と呼ばれていることはご存知でしょうか? この時期は
-

-
スーパームーンとはどんな現象か?地震や噴火とも関係がある?
皆さんはスーパームーンをご存知でしょうか? これは月が普通よりも大きく見える現象のこと
-

-
花火の日が5月28日と8月1日の2つあるのはなぜ?その理由や由来とは?
「花火の日」は5月28日と8月1日があるそうなのですが、その理由とは何なのでしょう。
-

-
年賀状を出す意味って何?現代は出す必要がない?
毎年年末になると用意しなければならないのが、年賀状ですが、そもそも年賀状ってどうして出すのでしょう?
-

-
セレブな国モナコが世界で最も治安の良い国と言われる理由とは?
モナコはF1のモナコ・グランプリや伝説の女優グレース・ケリーが公妃となったことなどで知られて
-

-
日本のハロウィンの発祥は東京ディズニーランド?その理由や有名なハロウィンイベントについても
日本ではすっかり定番イベントとなったハロウィンですが、実は日本でのハロウィンイベントは東京ディズ
-

-
サンタクロースの服はなぜ赤い?なぜ靴下にプレゼントを入れるの?
今年もクリスマスがやってきましたが、クリスマスと言えばやっぱりサンタさんですよね。 子ども
-

-
【画像あり】月の裏側が地球から見られない本当の理由とは?裏側の模様はどうなっている?
フジテレビの「世界の何だコレ!? ミステリー」で、月の裏側が地球から見れない理由を「月が自転して