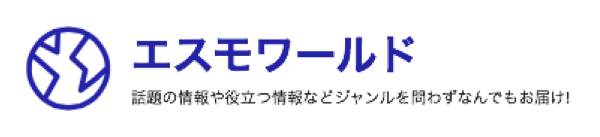立冬はいつある?日付はどのようにして決まる?意味や名前の由来なども
公開日:
:
最終更新日:2015/11/09
豆知識
「立冬」という言葉がありますが、これはいつあるのかご存知でしょうか?
その日付は毎年変わるそうですが、それはどのようにして決まるのでしょう?
今回は気になるこれらの詳細や立冬の意味、名前の由来などについてまとめてみました。
立冬とは?
立冬(りっとう)とは二十四節気の一つで、立春を1番として19番目にあたる節気のことを指します。
立冬の意味は立つ冬という言葉の通り、冬がはじまる日という意味があります。
冬がはじまる日である立冬は、立春、立夏、立秋の四立と言われる二十四節気で重要な節気にあたります。
立冬という名前の由来は、二十四節気を決めたときにその季節を表す名称として、冬がはじまる日であったその日を新しい季節がはじまるという意味の立つと冬を組み合わせて「立冬」となったようです。
ちなみに二十四節気はもともと中国で考案されたもので、日本とは気候が異なるため、節気と実際の季節感に多少違いを感じることもあるそうです。
立冬の日付、決め方について
立冬は毎年11月7日頃にあるのですが、その年によって若干その日付が変わります。
立冬の日付は2014年は11月7日、2015年は11月8日、2016年は11月7日といったように1日ほど前後するときがあります。
気になるのはその決め方ですが、太陽の天体上の通り道である黄道の太陽の位置によって決めます。
そもそも二十四節気はこの360度ある黄道を24分割して、15度ごとに分割し、それぞれ決められた位置を太陽が通過した時に節気が決まるのです。
立冬はこの黄道上で太陽が225度を通過したときのことを表しています。
立冬が過ぎるとだんだん寒くなってくることが考えられます。
立冬が過ぎたときは冬服の準備などをして、しっかり冬の対策をしておくといいでしょう^_^
関連記事
-

-
ハロウィンの名前の由来は?仮装する意味などについても
10月に行われるイベントと言えばハロウィンですが、 その名前の由来や仮装する意味などが気に
-

-
6月21日はスナックの日!由来は歯固め!?スナック菓子は歯に良いのか?
6月21日はスナックの日なのだそうですが、その由来はなんと歯を丈夫にするための「歯固め」とい
-

-
夏至の月は一年で最も赤く見えやすい?その理由とは?
夏至は昼の時間が1年で一番長い日であることはよく知られていますが、実は月の色が最も赤く見えやすい
-

-
5月6日のみずがめ座η(エータ)流星群を肉眼で見るコツについて
ゴールデンウィークの期間中である5月6日(土)には「みずがめ座η(エータ)流星群」がありますが、
-

-
ふたご座流星群とは?今度はいつ見れる?見える方角、時間帯などについて
2015年12月14〜15日は流星群の中でも最大と言われるふたご座流星群が見えるとのことですが、ふた
-

-
6月10日はミルクキャラメルの日!昔はタバコの代用品として売られていた!?
6月10日はミルクキャラメルの日だそうですが、その由来とは何なのでしょう? 昔はタバコ
-

-
梅雨の由来とは?もともとはカビを意味する「黴雨(ばいう)」だった?
毎年6月頃になると頻繁に雨が降る時期である梅雨がやってきますが、その由来とは何なのでしょう?
-

-
3月27日はさくらの日!なんとも微妙なその由来とは?
みなさんは3月27日が「さくらの日」と呼ばれていることはご存知でしょうか? この時期は
-

-
日本の光化学スモッグはどれくらい危険?中国との比較は?
日差しが強い時期になってくると光化学スモッグというものをよく見かけるようになりますが、日本の光化
-

-
午前・午後を表すAM・PMはラテン語が略されたものだった!?
時間を表すときによくAM・PMという言葉が使われますよね? 普段何も意識せずに見ていること